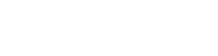江戸前鮨と初鰹 – 江戸っ子が熱狂した旬の味
「初鰹は女房を質に入れても食え」ということわざがあるように、江戸時代の庶民にとって初鰹は特別な食材でした。春の訪れとともに相模湾へやってくる初鰹は、江戸っ子にとっての風物詩であり、見栄と粋を象徴する存在でもありました。
本ブログは歴史上のことで諸説ございます。話のネタにお読みくださいませ。
初鰹の歴史 – 江戸時代のステータスシンボル
江戸時代、初鰹は非常に高価な魚でした。5月ごろになると、江戸の魚河岸には相模湾や紀州沖から運ばれた鰹が並びました。しかし、当時の小さな漁船では大量の漁獲が難しく、流通量が限られていたため、値段が高騰。特に初物をありがたがる江戸っ子の気質も手伝い、「まな板に 小判一枚 初鰹」と詠まれるほどの高値がついたと言われています。
粋を重んじる江戸っ子にとって、初鰹を食べることは単なる食事ではなく、文化の一部でした。初鰹を食べることは、季節の移り変わりを楽しむ粋な習慣だったのです。
初鰹と戻り鰹 – 年に二度の旬
鰹は回遊魚であり、水温20度前後の海を求めて移動します。春先に南の海から日本へやってくるのが「初鰹」、秋に南へ戻る途中に再び獲れるのが「戻り鰹」です。
- 初鰹(春・5月頃)
さっぱりとした味わいが特徴。脂が少なく、爽やかな風味で、江戸時代から愛されてきました。 - 戻り鰹(秋・9~11月)
脂がたっぷりとのった濃厚な味わい。近年では「迷い鰹」と呼ばれる、夏場に中間地点で獲れる鰹も注目されています。
江戸時代の人々は、さっぱりとした初鰹を好んで食べ、秋の戻り鰹よりも高く評価していました。
江戸前鮨における鰹
「鰹は刺身、刺身は鰹」と言われるほど、新鮮な鰹は刺身が最も美味しい食べ方とされています。現代では、しょうが醤油やにんにく醤油が定番ですが、江戸時代には「からし味噌」で食べるのが主流でした。
江戸の古川柳には、
初鰹 銭とからしで 二度泪
という一句が残っています。高値の初鰹を買うときの涙、そして辛いからし味噌で食べるときの涙、二重の意味で「泣ける」食材だったことが伺えます。
鰹の炙りと江戸前鮨
鰹を使った江戸前鮨の定番調理法のひとつが「稲藁での炙り」です。これは高知県の郷土料理「鰹のタタキ」が元になっています。炙ることで鰹の香ばしさが引き立ち、酢飯との相性が抜群になります。
稲藁で炙った鰹は、わさび醤油、柚子ポン酢、または塩でシンプルに味わうのがおすすめです。鮨屋では、職人が目の前で炙って提供することも多く、香ばしい香りとともに味わうことができます。
江戸前鮨と初鰹の粋
江戸時代から現代に至るまで、初鰹は「旬を楽しむ文化」として受け継がれています。マグロが江戸前鮨の王道とすれば、初鰹は江戸っ子の心をくすぐる「粋の象徴」と言えるでしょう。
江戸前鮨を楽しむ際には、ぜひ初鰹にも注目し、その歴史や文化とともに味わってみてはいかがでしょうか?
銀座からくの「カツオ」へのひと手間
当店では、鰹を煮切り醤油で和える【醤油漬け】にし、薬味を添えてお客様に召し上がって頂いております。これにより鰹が持つ臭みが抑えられ、旨味がさらに増します。江戸前鮨の伝統的な調理方法です。